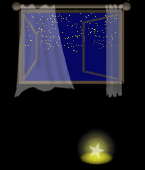
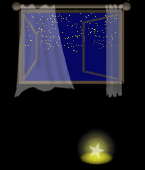
| 星に願いを |
「おにーさん、どうぞ♪」 「え‥‥‥‥‥?」 満面の営業スマイルととも差し出されたのは、こよりのついた、一枚の紙切れだった。 夕暮れ時の駅前は、買い物に出てきた主婦や学校帰りの学生やらで賑わっていた。 オレも、塔矢の碁会所でアイツとさんざん打って、家へ帰るところだった。 塔矢アキラと検討すると、オレもアイツも容赦ないから、それがなかなかおもしろかったりする。 今日もその内の一局を思い出しながら、人混みをぬってぼんやりと歩いていた。 そんな時にいきなり紙切れを突き出されたものだから、オレは急に意識を引き戻されて、思わず立ち止まってしまったのだった。 なんのことやら、状況が理解できなくてぱちくりと瞳を瞬かせたオレに、声をかけてきた〈おねーさん〉は、なおも笑顔のまま、紙切れをオレの手に押しつけた。 「お時間ありましたら、ぜひどうぞ!書けたら、あちらの笹の、好きな場所に吊してくださいね」 そう言われて見れば、なかなか立派な竹が、これでもか、というくらいにきらびやかに飾りてられ、その〈店〉の入口の両脇に立てられていた。 金銀のテープや、カラフルな輪飾りが、夕風に揺れているのが目に鮮やかだった。 そのまわりには長机が並んでいて、オレみたいに短冊をもらったらしい親子や学生のカップルやらが、ペンを片手に屈み込んでいた。 「ああ‥‥今日、〈七夕〉だったんだ‥‥‥‥」 短冊に願い事を書いて、笹に吊せば、願いが届く。 「どうですか?お兄さん、カッコイイからカノジョさんとかいるでしょう?恋愛がうまくいきますようにとか、どうですか?」 オレは、思わず吹き出してしまった。 「オレ、カノジョいないよ」 「ええーっ、ウソぉ?!えっ、え、じゃあ、カノジョができますようにとか、書きましょうよ」 なんとも、仕事熱心な〈おねーさん〉だ。 「‥‥じゃ、家で書くよ。これ、もらってってもいいの?」 「あ、はい!どうぞどうぞ!」 なんだ、絶対あの竹に吊さなきゃいけないってわけじゃないんだ。 ‥‥だったら、なんのための催しだ? よく分からなかったけれど、とりあえず適当に愛想笑いをしてその場を離れた。 すぐに後ろから、あの〈おねーさん〉の「どうぞ!短冊に願い事を書きませんか?」との声が聞こえてきた。 きっと次の相手にアタックしているのだろう。 なりゆきでもらってしまった、薄ピンク色の短冊が、1枚。 それをシャツの胸ポケットに突っ込んで、オレはまた雑踏の流れの中へと合流した。 7月7日。七夕。 窓の外には、ひときわ明るい1等星が3つ、三角形を描いて輝いていた。 梅雨の明けない都心で、〈七夕〉の夜空に星を見ることができるのは、東京では数十年ぶりと、テレビでキャスターが騒いでいた。 『奇跡』のようなものだ、とも言っていた。 オレは、電気を消した自分の部屋のベッドに足を投げ出して座り、窓から空を見上げていた。 町明かりのせいで、3つ星以外の星はよく見えなかった。 もちろん、天の川なんて見えやしない。 見えないけれど、あの空の高いところには、確かに〈川〉は流れている。 昔、そう教えてやったら、やけに嬉しそうな顔で喜んでいたヤツがいたのを思いだした。 〈アイツ〉は、天の川はそれはそれは美しいのだと、力説していた。 目に映らなくても、失われたわけでないならそれでいい、と、でも少し寂しそうに言っていた。 見たことがない、と言ったら、それはもったいない、と言っていたけれど、今のところオレは、天の川をまだ生で見たことがない。 ああ、そうそう、それでその後〈アイツ〉が「でも何故、天の川の水は落ちてこないんでしょうね」なんてことを、大真面目な顔で訊いてきたんだった。 そんなことを思い出して、オレはクスクスと笑ってしまった。 七夕。 織り姫と彦星が、1年にたった1度だけ出逢う、約束の日。 いつもなら、曇ったり雨が降ったりで、その出逢いはキャンセルになる。 けれど今年は、晴天。 それは、〈奇跡〉。 だったら。 だったら、もう一つくらい。 もう一つくらい。 〈奇跡〉が起こったっていいのに。 オレはふと思い出して、胸のポケットからあの短冊を取り出した。 少しくたびれた短冊のこよりをつまんで、なんとなく、目の前に吊してみた。 白紙の紙切れが、ふわりと舞い込んだ涼風にくるくると回った。 星に願いを届ける、笹につるした短冊。 でもオレは、書けなかった。 書けないだろうな、とは、自分で分かっていた。 叶うなら、書くだろう。 でも、叶わないことを、オレはもう知っているから。 オレの〈願い〉。 オレ自身ではどうにもならない、願うしか叶えることのできない〈願い〉は、ただ1つだから。 「‥‥だいたい、誰が叶えてくれるってんだよ」 星に〈願い〉を届けたところで、空では恋人達の1年ぶりの逢瀬の真っ最中だ。 そんなヤツらに他人の〈願い〉を叶える余裕なんてないだろうに。 開いた窓から、昼間の猛暑で消耗した身を労るかのような優しげな風が、ふわり、ふわり、と入り込んできていた。 オレは、くるくると回る紙切れを見つめた。 書けない〈願い〉。 それでも、願ってしまう────〈奇跡〉が欲しい、と。 〈奇跡〉が、起こればいいのに。 だからだろうか。 その〈気配〉に、オレは何気なく振り返った。 風が、後ろから吹き込んだような気がしたのだ────閉めたはずのドアと、壁しかないはずの、〈後ろ〉から。 床に置いた碁盤の対面に、佐為が座っていた。 佐為は、静かに瞳を閉じていた。 驚いた。 驚かなかったら、ウソだろう。 あれほど探して、あれほど望んでもこの手に返ることのなかったヤツが、いきなり自分の手の届く場所に現れたのだから。 これは〈夢〉だろうか、と考えてみた。 でもオレは、夢なら〈夢〉と分かるはずなのに、よく分からなかった。 〈夢〉にしては、妙にリアルだった。 たゆたうように吹いてくる、夜風の涼やかさも。 微かに緑の匂いを含んだ、しっとりとした空気の匂いも。 遠く微かに聞こえている、町の人々の息吹も。 ────佐為の変わらない、凛と冴えた容姿も。 でも、数億分の一くらいの確信を、オレはたぶん持っていたんだろう。 『七夕』だから。 1年に1度、逢うことを許される〈約束の日〉だから。 だから、もしかしたら────。 だからオレは、なぜかこの時、ストンと納得してしまってもいた。 そう、でなければきっと、もっともっと取り乱していたに違いない。 オレは、ただじっと佐為を見つめていた。 佐為は瞑目したまま、凛と背筋を伸ばして正座していた。 動かないのだろうか。 そう思ってしまうくらい、佐為は動かなかった。 ────そうして、どのくらいたった頃だろう。 ふいに、佐為の瞼が微かに震えた。 睫が揺れ、ゆっくりと瞼が持ち上がった。 瞳はやがて周囲を映し、徐々に大きく丸くなっていった。 慌てたように、首をめぐらせる。 ────まるで、そこにいるのが信じられない、とでも言うように。 「佐為」 呼ぶと、佐為は弾かれたように、振り返った。 震える唇が、3文字の形を追う。 ────『ヒ』『カ』『ル』。 ああ、やっぱり『佐為』だ。 これは〈夢〉じゃない。 でもきっと、〈現実〉でもないだろう。 そう────これは、〈奇跡〉。 オレは口を開いた。 思ったよりも簡単に、声は唇から零れた。 「おかえり。‥‥佐為」 佐為の満面に、雲晴れて現れた太陽のように輝いた笑みが、パアッと広がった。 そうして見る間に涙が沸き上がったかと思うと、あとからあとから溢れてこぼれ落ち始めたのである。 オレは久々に、『頭の中で泣かれる』感覚を味わった。 昔はそれがやたらと鬱陶しかったんだけれど、今はむしろ、それが嬉しかった。 またヒカルに逢えて嬉しい、と、佐為は言った。 ヒカルにずっと逢いたかったのだ、と、涙でふやけた笑顔で言った。 「オレも、佐為に逢いたかったよ」 そう言ってやると、佐為はまたボロボロと涙をこぼした。 「あんまり泣くと、目ぇ溶けるぞ」 そう言うと、佐為は慌てたように、袖口で目元を拭っていた。 オレはベッドから降りて、床に立った。 佐為がオレを見上げて、ずいぶん大きくなりましたね、と、まだ潤む瞳を見開いて言った。 「オレ、もうハタチ過ぎたんだぜ」 そう言うと、佐為は驚いたように、ほう、と声をあげた。 ほんの僅かの間に、ヒカルはどんどん大きくなっていくのですね、と、まるでイナカの年寄りのようなことを言った。 まあ確かに、千年も生きてきた‥‥や、生きてないか、‥‥『存在していた』?ヤツにしてみれば、5〜6年の時間なんて、瞬きの間くらいのようなものだろうが。 オレは佐為の対面に腰を下ろした。 「佐為。打とうぜ」 佐為は、嬉しそうに瞳を輝かせて頷いた。 「オレ、強くなったんだぜ」 そう言ったら、佐為はますます楽しそうに顔をほころばせた。 楽しげに笑いながら、では私も本気でいきましょうか、と言った。 「望むところだ」 体の芯を痺れさせるほどの緊張と高揚感が、急激に膨れあがる。 その感覚がいつも以上に激しいのは、相手が他ならない、佐為だからだ。 願ってやまなかった相手との一局。 オレは右手をぐっと握りしめた。 「お願いします」 頭を下げる。 佐為も、お願いします、と頭を下げた。 さらり、と、衣擦れが聞こえたような気がした。 本当の夜空をうすぼんやりと覆い隠す町明かりのヴェールの向こうで、恋人達が逢瀬を楽しんでいるだろう頃。 オレは佐為と碁盤を挟んで向かい合っていた。 やっぱり佐為は強くて、オレは一度も勝つことができなかった。 「やっぱ、佐為はすごいな」 塔矢アキラより大胆で。 高永夏より華麗で。 緒方さんより繊細で。 きっと、塔矢先生と変わらないくらい、緻密に攻守のバランスがとれていて。 そしてきっと誰よりも、美しい碁を打つ。 すると佐為はふわり、と微笑んで、私は『ヒカルの碁』が大好きですよ、と言った。 「オレの碁?」 ええ、この辺りの押しの強さ、こちらの細やかさ、変幻自在な打ち回し‥‥どれも素晴らしくて、なんとも心躍る碁でした。 盤上には、終局した1局の棋譜が残っている。 それを見て、佐為は言った。 ヒカルは、たくさんの人達と、良い〈出会い〉をしてきたのですね────と。 「そうかもな‥‥うん、いろんなヤツと打ったよ」 佐為がいなくなって。 それからも、いろんなヤツと競ったり、時に助けられて、オレは歩いてきた。 きっとそれは、この先も変わらないだろう。 けれど。 「‥‥でも、オレの土台は佐為だよ」 まっさらだったオレに〈未来〉を繋いだのは、佐為だ。 遠い〈過去〉と、遠い〈未来〉を繋ぐために。 佐為が思いを託したのは、このオレなのだ。 「この先、もっともっといろんなヤツと打つだろうけど、もちろんオレはオレの力で戦うけど、でも、やっぱり根っこの部分は〈佐為〉なんだよ。佐為がいたから、今のオレがいるんだ。佐為がたくさんのものをオレにくれたから、だからオレは‥‥‥‥」 囲碁への情熱。 上を目指すための力。 そして、他人を慈しみ、思いやる気持ち。 オレはいったい、どれだけの愛情に守り支えられていたのだろう。 「佐為」 オレは視線を落として、シャツの裾をキュッとつかんだ。 「‥‥ありがとう、な」 ヒカル‥‥、と佐為の呟きが聞こえた。 碁盤の向こうに、佐為の真っ白い着物の膝元が見えていた。 オレはかまわず、話し続けた。 「オレ、佐為に逢えてよかった。自分勝手で、おまえのことなんかちっとも考えてやらないコドモで、虎次郎みたいにやさしくしてもやらなかったけど‥‥でも、楽しかったよ。本当に、楽しかったんだ」 楽しかった日々。 つかの間の、輝石のような時間────それは確かな〈奇跡〉。 今は痛いほど、それがよく分かるのだ。 ずっと、一緒にいたい。 それは、切実なまでの、ただ一つの〈願い〉。 けれど、それが叶わないだろうことも、オレはやっぱり分かってしまっていた。 空の恋人達の逢瀬が一夜きりであるのと同じように、きっと朝になれば、佐為はいなくなってしまうのだろう────あの日のように。 窓の外を振り仰げば、相変わらず黒い空が広がっていた。 けれどいつの間にか、あの三つ星は天頂から姿を消し、かわりにうすぼんやりとした小さな星がまばらに瞬いていた。 「佐為。もう一局打とうぜ」 オレは盤上の棋譜を崩し、手早く黒石をかき集めた。 次いで、白石も集め、傍らの碁笥に流し入れた。 「オレが黒でいいよな」 いなくなってしまうなら。 せめて、できるだけたくさん、打ちたい。 打って、打って、目の前からいなくなる瞬間まで、佐為と打っていたかった。 オレは、更地の十九路に1つ目の黒石を打ち込んだ。 ────右上スミ、小目。 「佐為、おまえの番だぜ」 白石の碁笥に指先を浸して、オレは顔をあげる。 ────ふわり、と。 「‥‥‥‥‥佐為?」 突然、視界が真っ白なもので覆われた。 オレは、何が起こったのか、とっさに判断できずに固まってしまった。 サラ‥‥、と、衣擦れが、静かな部屋の中でやけに響いた。 ふわり、と柔らかなものがオレの体を包み込んだ。 トン、と軽く背を押されて、そのまま前に倒れたオレは、気がつけば体ごと何かに支えられていた。 「‥‥‥佐為────?」 佐為に抱きしめられているのだ、と、ようやく分かったのは、鼻先を夏蜜柑にも似た爽やかな香りが掠めてからだった。 オレは、慌てた。 あまりに慌てすぎていて、混乱していて、だから逆に動けなかった。 なんで? 佐為は、碁石にも触れないはずなのに。 佐為に触れることだってできないはずなのに。 なのになぜ オレは『佐為に抱きしめられている』んだ? 愕然と瞳を瞠ったまま固まるオレを、佐為は包み込むように抱きしめていた。 ────ああ、でも。 まあ、いいか、と思ってしまった。 これは〈奇跡〉だから。 こんな最高なオマケがあったって、いいじゃないか。 佐為の懐は、泣きたくなるくらい心地よかった。 鼻の奥がツン、とくるのを堪えて、オレは力を抜いた。 そんなオレを、佐為は確かに受けとめてくれた。 「ヒカル」 呼ばれて、オレは佐為の顔を振り仰いだ。 薄暗い部屋の中で、佐為は真白く光る月のように、どこか清冽に浮かび上がって見えた。 そしてその顔は、切ないほどに懐かしい、綺麗な微笑を浮かべていた。 ────私も、楽しかったですよ。ヒカルと出逢えて、本当に良かった 「佐為────」 ────ごめんね、それから、ありがとう。ヒカル、私はあなたが大好きでしたよ。 「‥‥‥‥‥‥‥っ」 ヤバイ、と思った。 泣きそうだった。 オレは佐為の微笑から視線を逸らして、広い懐に顔を埋めた。 「‥‥‥‥なあ、それって過去形?」 佐為はクスリ、と笑って、僅かな迷いもなく答えた。 「〈過去〉も、〈現在〉も、〈未来〉も、私はヒカルが大好きですよ」 最後のオレの強がりも、あっけなかった。 オレは、泣いた。 久々に、声をあげて泣いた。 なんだかもう、自分でもなんでこんなに泣くのか分からなくなるくらい、佐為にすがってわあわあと泣いた。 ヒカル、と佐為が呼ぶ。 ヒカル。 ヒカル。 慰めるように、愛おしげに佐為が呼ぶ。 それだけで、自分が大切にされているのが分かるから。 だから、もっと呼んで。 いつまでも、呼んで。呼び続けていて。 名前を────その声で、「ヒカル」、と。 それからどれだけ、オレは泣いたのだろう。 気がつけば、部屋はすっかり朝になっていて、夏の日差しがさんさんと満ち溢れていた。 オレは眩しさに瞳を眇めながら、ゆっくりと辺りを見渡した。 いつもと変わらない、自分の部屋。 傍らのベッド。開いたままの窓。壊れたテレビ。マンガが入った冷蔵庫。 オレは、〈一人〉だった。 めぐらせた視線を碁盤に向けて、オレは、あ、と小さく声をあげた 盤上には、2つの石が輝いていた。 右上スミの、黒石。 そして、 「左下スミ‥‥小目‥‥‥‥‥‥」 天元を中心として、まるで対のように、白石が輝いていた。 あれは、〈夢〉だったのかもしれない。 オレの願望が見せた、泡沫の幻。 ベッドにもたれるように寝ていたのだって、夜中棋譜並べでもしているうちに寝てしまったのかもしれないし、白石だって、オレが寝ぼけて置いたのかもしれない。 それでも。 「ンッ‥‥‥‥‥‥‥‥っ!!」 オレは両手を組んで頭の上に掲げ、思いきり体を伸ばした。 なんだか、すっきりしていた。 首を回したらパキパキと鳴るくらい肩はこっていたけれど、不思議と、世界中がまぶしいと思えるほどに、心は晴れ晴れとしていた。 オレはまた、盤面に目を落とした。 黒、白、双方の第一手。 〈始まり〉の、第一歩。 ここからまた、新たに始まるのだ。 オレと────佐為の、〈未来〉への道程が。 窓の下を、バイクのエンジン音が通り過ぎていった。 青い空を、小鳥が甲高く鳴き交わしながら飛び去っていった。 立ち上がったオレは、ふと、ベッドの上にあの〈短冊〉を見つけた。 何も書かれていない、白紙の〈短冊〉。 オレはそれを拾い上げると、ベッドに上がり、カーテンレールにそれを吊した。 朝の爽やかな風に吹かれて、〈短冊〉はふわふわとあおられた。 それを見ているうちに、なんだか無性に、誰かと打ちたくなった。 ふと頭に浮かんだのは、見た目はやさしげなのに、オレが知る中で一番大胆で力強い碁を打つヤツだった。 「‥‥‥‥電話、してみるか」 時計に目をやれば、午前5時をまわったところ。 アイツは朝早いから、きっともう起きているだろう。 そうだ、昨夜の〈佐為〉との一局を並べて見せてやろう。 アイツは〈佐為〉だと気づくだろうか。 気づくだろうな、アイツなら。 そうして、オレを問いつめるんだ。 「saiとどこで会ったんだ?!」って。 そう思うと、もうすぐにでも塔矢に会いたくなって、オレはバタバタと着替えだした。 予定変更。 直接、家に行ってやろう。 「連絡もなしに来るなんて、非常識だぞ!」とか言いそうだけど、かまうものか。 適当に手近にあったものを着て、オレはドアを開けた。 背中から、ふわり、と風が追いかけてきた。 オレは思わず立ち止まり、後ろを振り返った。 光に満ちた、自分の部屋。 その真ん中に置かれた碁盤と、2つの碁石。 なんだか、そこにアイツがいるような気がした。 ニコリと笑いかけて、「行ってらっしゃい、ヒカル」と言われたような気がした。 行ってらっしゃい。 「うん‥‥‥‥‥」 思わず顔がほころんでしまう。 行ってくる。 オレは再び背を向け、部屋の外へと足を踏み出した。 |
| 2003.7.6 |