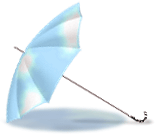
| 雨の日に |
ピンポーン 「おーい、塔矢ぁ」 玄関口で呼び鈴を鳴らすと、 「進藤?」 声は戸の向こうからではなく、意外な方から投げかけられた。 思わずそちらを振り返るが、声の主は見あたらない。 「塔矢?」 もう一度呼ぶと、まもなく玄関脇の庭木の向こうから、アキラがひょっこり姿を現した。 アキラは、片手に花鋏を持ち、反対の手には一抱えほどもありそうな紫陽花の花を抱えていた。 晴れた夏空のように鮮やかな青色をしたその花は、折からの雨に濡れて瑞々しくこんもりと咲き誇り、それがまたやけにアキラには似合っていた。 途端にうろんな目つきになったヒカルに、アキラは不思議そうにその形のよい頭を傾けた。 「‥‥どうした、進藤?」 「おまえってさあ‥‥‥」 「なに?」 「なんか‥‥‥‥フツーに、似合うよな。‥‥そーゆーの」 そう言って溜息をついたヒカルに、アキラはよく分からないというような顔をしながら、手にした紫陽花に目を向けた。 「これ?ただの紫陽花じゃないか」 「塔矢が持ってると、ただのアジサイにも見えねェよ」 「じゃあ、何に見えるって言うんだ」 「え、あー‥‥‥」 ヒカルは「あ」の形に口を開いたまま、肩に載せていた傘をくるくると回した。 大粒の水滴がキラキラと、ヒカルのまわりに舞い散った。 「‥‥‥‥‥アジサイ、かなぁ」 「‥‥‥何が言いたいんだ、キミは」 アキラはフン、と鼻で吐息をつくと、ヒカルの隣をすり抜け、玄関の戸を開けた。 すり抜けざま、ヒカルの鼻先を、濡れた髪の匂いがふわりと掠めた。 「どうぞ」 「‥‥塔矢、おまえ、アタマ拭いたほうがいいんじゃねェ?」 「ああ‥‥そんなに濡れてるかな」 「びしょ濡れってわけじゃないけど‥‥だいたい、雨降ってんじゃん。なんでカサささねーんだよ?」 「霧雨だし、すぐ中に入るから大丈夫だと思ったんだよ」 ヒカルが中へ入るのを見送ってから、アキラもその後に続く。 戸を閉めると、廊下の向こうから、人の気配のない、ひんやりとした空気が漂ってきた。 「先に居間の方へ行っていてくれ。ボクはこれを水に入れてくるから」 玄関のたたきに、アキラの脱いだつっかけが几帳面に並ぶ。 「なんで花なんか切ってたんだ?」 「ああ、明日父と母が帰ってくるって言うから。梅雨時でうっとおしいだろう?せめて玄関に花でも生けておいてあげようと思ってね」 「ふーん‥‥‥」 それきり、台所の方へと向かうアキラの背に、ヒカルはふと思い出したように言った。 「ミズキリしといたほうがいいぞ。アジサイはすぐヘタるから」 アキラが足を止めて振り返った。 ────ものすごく、珍妙な物を見たような顔つきで。 その表情に、ヒカルは眉根を寄せた。 「な‥‥なんだよ」 「いや‥‥‥‥意外だなと思って」 「なにが」 「なにがって‥‥なぜ『水切り』なんて知っているんだ?」 「‥‥知ってちゃ悪いかよ」 「悪くはないけど‥‥」 「じゃ、いいじゃん」 ヒカルは無造作に湿ったスニーカーを脱ぎ、玄関の端に揃えて置いた。 「‥‥‥知ってるヤツがさ、花好きだったんだよ。ついでに言うと、茎の先火であぶっとくのもいいらしいぜ」 「へぇ‥‥‥‥そう‥‥‥‥‥‥‥」 まばたきを忘れたかのように瞳を丸くしたアキラの前を通り過ぎながら、ヒカルが言った。 「じゃ、先行ってるな。塔矢、ちゃんと髪拭いてきた方がいいぞ」 「あ、ああ‥‥────」 アキラは呆然としたまま、ヒカルが居間へと消えるまで見送るのだった。 アキラが戻ってくると、ヒカルは碁盤の前に座り、ぼんやりと庭先を眺めていた。 雨が、しとしとと降り続いていた。 「進藤」 お茶の載った盆を手に声をかけると、ヒカルが小さく肩を揺らして振り返った。 「あ‥‥ビックリした。急に声かけんなよ」 「足音はしただろう」 心外だといわんばかりに瞳を細めて、アキラは二人の間に盆を置く。 ヒカルが手を伸ばして、湯のみを取り上げた。 アキラは碁盤の前に端座した。 「何を見ていたんだい?」 「庭」 そう言われて、ガラス戸の外に目を向ける。 木々の緑が雨に濡れ、生き生きと生い茂っている。 一角を、細雨に包まれた紫陽花の一群が鮮やかに彩っていた。 「紫陽花、好きなのか?」 「キライじゃないよ。好きってほどじゃないけど」 「なんなら持って帰るかい?帰る時、切ってあげるよ」 「いいよ、別に。切ったらもったいないだろ」 「たくさんあるから、かまわないよ」 「いいんだって。あのままのほうがキレイだろ」 「そう‥‥‥?」 天の恵みに、紫陽花が謳う。 「ほら、打とうぜ」 ヒカルが碁笥の蓋を開ける。 「ああ‥‥そうだな」 アキラも蓋をそっと床に裏返して置いた。 「お願いします」 「お願いします」 パチン 初めの一音が、閉じられた空間を波紋のように広がった。 翌朝、ヒカルが帰ろうとすると、アキラが新聞紙でくるんだ紫陽花の花を差し出した。 「なんだよ、いらねーよ、オレ」 「せっかく切ったんだから、持って行け」 「えー‥‥めんどくさいなあ」 ブツブツと文句を言いながら、ヒカルは花束を受け取る。 「帰ったら、水切りしろよ」 「チェッ、分かってるよ」 ヒカルが踵を返すと、新聞紙の中で揺れた紫陽花が、ガサガサと派手に音をたてた。 下駄箱の上では昨日の紫陽花が、真っ青な頭を意気揚々ともたげ、二人のやりとりを見つめていた。 ガラガラ、と、ヒカルは玄関の戸を開けた。 「おー、晴れてる」 ヒカルが外へ出たのに続いて、アキラもサンダルをつっかけて外へ出た。 木々の葉先から、水滴がキラリと光って落ちる。 通りに出ると、濡れたアスファルトが朝日を受けて鏡のように眩しく輝いていた。 「じゃあ、気をつけて」 「ああ、じゃあ、またな」 歩き出したヒカルはちらとだけ振り返って、傘を高く振り上げた。 傘の先から飛んだ雫が、青い空にキラリと弧を描いた。 「お母さん、これ」 「紫陽花じゃない。ずいぶん立派ね。どうしたの、これ?」 「塔矢にもらった」 出迎えた母親に花束を押しつけて階段を上がりかけ、ふとヒカルはつけ加える。 「ちゃんと水切りしといてよね」 「え‥‥ええ‥‥‥────」 母は不思議そうに首を傾げて、息子を見送った。 空色の紫陽花は今、進藤家の下駄箱の上で、クスクスと笑い合うように、手鞠に似た頭を寄せ合っている。 |
| 2003.6.15 |