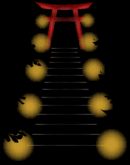 |
|
ゆく年くる年 |
|
「塔矢!」 駅の小さな改札口。 夜の11時をまわったというのに、電車が到着するたびにたくさんの人が押し出されてくる。 誰もが、どこかそわそわと浮かれているようだった。 その中からあがった自分の名に、アキラは目を落としていた詰碁集から顔をあげた。 声の主は、一目で見つけることができた。 「進藤」 手の中の本を閉じて、アキラは答える。 ヒカルが笑顔で駆け寄ってきた。 「よう。わりィ、オレ待たせた?」 「そうでもないよ。ああ、でも30分くらいになるかな?」 「え゛っ?!オレそんなに遅れたっ?」 ヒカルが慌てて腕時計に目を走らせる。 けれど確認する前に、時計の盤面ごとアキラの手の平に掴まれてしまった。 「おい────」 「大丈夫、ボクが20分ほど早く来てしまっただけだから────ほら、行こう」 淡く微笑んで、アキラは歩き出した。 手首を掴まれたまま、引っ張られるようにヒカルは後に続いた。 人混みは雑然としているようで、けれどなんとなく一つの流れを作って、同じ方向へと向かっている。 アキラはヒカルを引いたまま、流れにのり迷いのない足取りで駅の外をめざした。 大晦日の夜から初詣に行こう、とアキラがヒカルを誘ったのは、まだ町がクリスマスの雰囲気に浮かれつつある頃だった。 クリスマスもきてないのに正月の話かよ、とヒカルは笑っていた。 それでもあっさり承諾したのは、ちょうどその日がアキラの誕生日だったからかもしれない。 後日の電話で行きたい所があるかと尋ねると、 「どこでもいいぜ。ああ、でも、あんまり混んでないとこがいいなあ」 とヒカルは言った。 だからアキラは、毎年訪れる近所の神社に、ヒカルを連れて行くことにしたのだ。 駅の外へ出るすぐ手前で、ふいにアキラは思いがけない方向へと腕を引っ張られた。 ヒカルがアキラに掴まれたまま、いきなり別の方向へと歩き出したからだ。 「あ、塔矢、ちょっと待って」 「進藤‥‥っ?」 あいかわらず、ヒカルの行動はアキラには理解しがたい。 ヒカルが向かう先には、自販機があった。 眉根を寄せるアキラなどおかまいなしに、ヒカルはダウンジャケットのポケットから財布を出す。 そして、 「ゴメン、ちょっと放して」 「え、あ、ああ」 アキラが手を放すと、小銭を取り出し、慣れた手つきで投入口に放り込んだ。 押したボタンは、温かい250ml缶のウーロン茶。 けたたましい音を立てて出てきたそれを、ヒカルはアキラの手に握らせた。 「え、なに?」 「おまえ、手冷たいから」 30分待たせたのオレだしな、とつけ加えて、ヒカルが照れたように笑った。 ヒカルの行動はいつも、突拍子もなくて。 だからいつも、取り繕う間もなく怒らされたり、嬉しくさせられたりする。 「‥‥ありがとう」 「んじゃ、行こうか。で、どっち?」 ヒカルはさっそく違う方向へと足を向ける。 アキラは空いた手でヒカルの袖をつかんだ。 「こっち」 言いながら、ヒカルを引っ張って歩き出す。 ヒカルはあたふたとついてきた。 「塔矢、なあ、オレいつまでこのまま?」 「駅を出るまで。でないとキミ、すぐ余所へ行きそうだ」 前を向いたまま、アキラが答える。 片手にヒカル。片手に温かいウーロン茶。 ヒカルは観念したのか、ただ困ったような顔をして隣に並んだ。 アキラの町の神社は、駅からしばらく歩いたところにあった。 遠くからでも分かるくらい夜空にぼんやりと浮かんで見えるのは、盛大にライトアップされているせいだ。 大晦日から、新年へと変わる、〈特別〉な日。 一年の無事を感謝し、新たに願をかけるべく、神社は小さいながらもかなりの人々で賑わっていた。 「みんなヒマだなぁ」 何気なくヒカルが口にすると、 「初詣は本来夜中の内に行くものなんだよ」 とアキラに呆れたように言われてしまった。 鳥居の手前には、気の早い夜店が並んでいた。 簡単に誘惑されるヒカルの腕を掴んで、アキラはさっさと鳥居をくぐった。 短い参道を抜け、アキラはヒカルを拝殿の手前の手水舎へと連れていった。 くりぬいた大きな石に満々と水がたたえられ、横に渡した竹筒の小さな穴から新しい水が細く流れ出ている。 入れ代わり立ち代わり人がやってきては、柄杓に受けた水で手をぬらしていた。 「はい」 アキラは柄杓をとり、ヒカルに手渡した。 ヒカルは素直に受け取ると、不思議そうに手の中のそれを見つめた。 「オレ、別に喉かわいてねぇよ?」 「‥‥‥‥は?」 自分の柄杓をとろうとしていたアキラの手が、ぴたりと止まった。 顔をあげると、ヒカルがきょとんとした目を向けてくる。 嘘でも冗談でもないだろうとは、見ればすぐに分かった。 「‥‥キミ、神社にお参りしたことないの?」 「あるよ」 バカにすんなよな、とヒカルがふくれる。 では、なぜこれが〈飲み水〉になるのだろう────アキラは眩暈に似た感覚に捕らわれる。 「‥‥これは、お参りする前に手を清めるための水だろう。知らないのか?」 「そうなの?ってか、これって、飲み水じゃねぇの?」 「違う」 アキラが唸るように断言すると、ヒカルは、なんだそうかよ、オレ飲んでたよいっつも、とかなんとか、実にあっけらかんと白状した。 アキラは思わず眉間を押さえた。 ヒカルといると、自分が常識だと思っていたものが、世間一般に言われるところの常識なのか、それとも自分が物知りなのかが分からなくなる。 「で、これ、どうすればいいんだ?」 ヒカルに問われて、アキラは深く溜息をついてから言った。 「‥‥ボクの真似をすればいいから」 「ああ、分かった」 アキラは柄杓をとり、水を満たすと、作法通りに両手を清め、口をすすいだ。 それをヒカルがじっと見ているものだから、なんとも居心地が悪い。 「なんか、めんどくせぇことすんのな。水出てんだから、それで洗えばいいのに」 「‥‥いちおうね、これ、神様の水だから」 「ふうん‥‥」 ヒカルはしげしげとアキラを見つめている。 アキラは手早く最後まですませて柄杓を戻し、ヒカルを促した。 「で、分かった?」 「う〜ん、たぶん?」 自信なさそうにヘラ、と笑って、ヒカルは柄杓に水をためた。 アキラはハンカチで手を拭きながら声をかけた。 「‥‥両手が洗えてれば、順番は気にしなくていいから」 「あ、そうなんだ」 ヒカルはホッとしたように頬をゆるめる。 もたもたと手を流すヒカルの横を、たくさんの人が訪れては去っていった。 アキラはヒカルの後ろでじっと待っていた。 やがてヒカルは柄杓を元に戻すと、幽霊の真似のような手つきで振り返った。 「塔矢、ハンカチとって」 「‥‥どこ?」 「オレのズボンの右のポケット」 「‥‥‥‥‥‥」 アキラはヒカルをそこから少し離れた木の下へと連れて行き、ダウンジャケットの裾をめくりあげてハンカチをとってやった。 「サンキュ、塔矢」 ヒカルが笑う。 「‥‥どういたしまして」 それしか、アキラは返す言葉を思いつかなかった。 時計を見ると、新年まではあと5分ほどあった。 「進藤、ちょっとつきあってくれる?」 「いいけど、どこへ?」 「うん、先にお守りを返してこようと思って」 「返す?」 また、ヒカルが不思議そうな表情になる。 「うん。こっち」 アキラは先に立って歩き出した。 ヒカルが慌てて隣に並んだ。 神社の裏に回ると、開けた場所で大きく火をたいていた。 「うわ、すっげーたき火」 思わず感嘆の声をもらしたヒカルの顔が、炎に照らされる。 金の前髪が、キラキラと輝いた。 「〈お焚き上げ〉って言うんだよ」 アキラはそう言って、コートのポケットから守袋をつかみ出した。 「おまえ、いくつ持ってきたんだよ」 ヒカルが呆れるほど、アキラのポケットからはたくさんの守袋が出てきた。 「いろいろとね、みんながくれるんだよ。心願成就とか、開運祈願とか、交通安全とか?」 「ふうん」 ヒカルの目の前で、アキラは軽くそれらを火の中に投げ入れた。 強い火に飲み込まれたそれらは、あっという間に見えなくなってしまう。 その行方を追うようにじっと炎を見つめていると、隣でヒカルがぼそりとつぶやいた。 「でもさ、おまえ、実はあんまりご利益とかアテにしてないだろ」 「そうかな?」 アキラは振り返る。 ヒカルは炎を見つめたまま口元に笑みを浮かべていた。 「だって、塔矢が強いの、塔矢ががんばってるからだろ」 アキラは目を見開いた。 ヒカルがアキラを「頑張ってる」と言えるのは、ヒカル自身が「頑張っている」からだ。 ヒカルは日々強くなっている。 けれどまだ、ヒカルはアキラを越えられない。 それは、アキラが越えさせないよう「頑張っている」からだ。 それを、ヒカルは感じているのだろう。 もうずっと、アキラはヒカルを求めてきた。 生涯のライバルとして。それ以上の存在として。 今はお互いに、その地位を得ようとしている。 そのためにヒカルが「頑張っている」のに、その代価が神の〈ご利益〉など、アキラのプライドが許さない。 だからこそ、「頑張っている」のだ。 そう、これは確かに、自分自身の力。 そのことを、ヒカルは分かってくれている。 「ああ、でも」 ふと、ヒカルが思いだしたように言った。 「交通安全は効いてるかもな」 「そうだね」 アキラは小さく失笑した。 火の粉が勢いよく舞い上がり、天を目指した。 突然、拝殿の方でガラガラと鈴を鳴らす音が聞こえてきた。 時計を見れば、ちょうど0時をさしていた。 あちこちで「おめでとう」の声があがった。 おめでとう。 明けましておめでとう。 アキラは軽く息を吸って、ヒカルとまっすぐに向かい合った。 「進藤。明けましておめでとう」 ヒカルはびっくりしたように目を見開いて、それからいつもの笑顔になった。 「明けましておめでとう。ちぇ、先越されたな」 アキラはクスリと笑った。 「今年もよろしく。まだまだ負けないからね」 「うぉっ、センセンフコクってやつかっ?オレだって、今年こそは打倒塔矢アキラだ!」 「アハハ、受けて立つよ────進藤、行こう」 アキラは笑いながら、たき火に背を向け歩き出した。 そう、受けて立てるように。 前を歩いていくのだ。自分の力で。 「塔矢!」 ヒカルが追いかけてきた。 勢いあまったのかそのまま追い越して、戻ってきて、背中からじゃれついてきた。 「こらっ、進藤!」 驚いて、反射的に手を伸ばす。 その手をすり抜けるように、ヒカルは離れ、アキラの前にまわった。 「塔矢!おっせーぞ!早く行こうぜ」 満面の笑顔。 惹きつけられて、目が離せなくなる。 「塔矢」 自分より楽しげなのが、なんとなく悔しくて。 早足で近づいたら、跳ねるような足取りで隣に並んできた。 「塔矢」 「なに?」 「オレ、がんばるから」 「うん‥‥‥‥‥」 その一言が、アキラの心を晴れやかにした。 拝殿前でしばらく順番を待ち、二人は一緒に鈴を鳴らし柏手を打った。 家族の平穏無事を祈ってアキラが顔をあげると、ヒカルはまだ神妙に手を合わせていた。 その姿が意外な気がして、アキラはまじまじとヒカルを見つめた。 やがて顔をあげたヒカルは、しばらく拝殿の奥を見つめて、やっとアキラを振り返った。 目が合うと、ヒカルは不思議そうに笑った。 「なに?」 「いや‥‥なんでもない」 行こう、と促して、アキラはその場を離れる。 「変なヤツ」 そう言って、ヒカルが後をついてきた。 「おみくじ引いてこう」 と言い出したのは、ヒカルだ。 そしてアキラが答えようとした時にはもう、姿が見えなくなっていた。 「塔矢!こっちこっち!」 みれば授与所の前でもう、ヒカルが手招きしている。 仕方なく近づいていくと、中にいた巫女姿の若い女性に声をかけられた。 「あら、アキラくん」 「ああ、どうも。こんばんわ。明けましておめでとうございます」 礼儀正しく頭を下げたアキラに、ヒカルが不思議そうに訊いてきた。 「塔矢の知り合い?」 「うん。この神社のお嬢さん」 「アキラくん家はウチの氏子だから。キミは?アキラくんのお友達?」 「う〜ん、まあ、そんなとこ」 ヒカルはヘヘヘ、と人なつこく笑った。 「おねーさん、おみくじちょうだい。オレ、二十三番。塔矢も、早く引けよ」 「いや、ボクは‥‥」 「なんだよ、つきあいわりィぞ」 そうまで言われると、引かないとかえって了見が狭いような気がして、仕方なくくじの入った筒をふる。 出てきた番号を告げて、くじを受け取ると〈大吉〉だった。 ヒカルがのぞき込んできた。 「塔矢、おまえ、なんだった?」 「ボク?」 言葉のかわりに、紙片を見せると、ヒカルは思いきり悔しがった。 「ちぇー、オレ〈吉〉だぜ。なんか、中途半端だよなあ」 「おみくじっていうのは、今の自分の状態だそうだから、そんなに気にすることもないんじゃない?」 「〈大吉〉引いたおまえに言われてもうれしくない」 そう言って、ヒカルは手元の紙片を睨みつけた。 そんな姿は、やっぱり幼い。 「ああ、でも」 ふいに、ヒカルの声が弾んだ。 「ちょっと当たってるかも。ていうか、当たっててほしいかな」 アキラはヒカルの手元をのぞき込んだ。 「どれが当たっててほしいの?」 「えー?これ」 ヒカルが指さしたのは、〈待人〉の項目だった。 〈待人〉叶い難し。が、いずれたよりあり 「進藤‥‥誰か待ってる人がいるの?」 「んー、まあ、ね」 ヘヘ、とヒカルが笑う。 そうやって、ヒカルは時々アキラが知らない顔をするのだ。 「ねえ、二人とも。絵馬書いていかない?」 絵馬、と聞いて、ヒカルは小首を傾げた。 「絵馬って、オレ書いたことない」 「そうねえ、合格祈願する時くらいしか書かないものね。でも、神様への手紙と思えばいいんじゃない?」 「神様への手紙‥‥‥‥」 だったら書く、とヒカルは手を伸ばして絵馬を受け取った。 ヒカルに絵馬を手渡した彼女は、続いてアキラにも差し出した。 「はい、アキラくん」 「ボクも?」 「書くでしょ?」 ニッコリと微笑まれ。 アキラは断る理由を思いつけなかった。 といっても、何を書けばいいのか、なかなか思いつかない。 ペンを片手に考え込んでいると、後ろから軽く肩をたたかれた。 「おっ先」 「え、進藤、もう書けたのか」 意外だった。 慌てて、真剣に考え込む。 ふと、思いついたのが、その一言だった。 ────進藤ヒカルとたくさん対局できますように 他の願いは、どれも自力で叶えたいものばかりだった。 けれどこればかりは、自分一人でできるものではないから。 アキラはペンを授与所に返してから、絵馬を下げに行った。 鈴なりに絵馬が下がるその場所に、どういうわけかヒカルは見あたらなかった。 とりあえず自分の分を下げてから探しに行こうと絵馬をくくりつけていると、ふと、目の端に一枚だけ裏向きになっているものを見つけた。 何気なく手を伸ばし、ひっくり返す。 否応なしに、その文字は目にとびこんできた。 面いっぱいに埋められた、大きくて乱暴な字。 その〈願い〉は、アキラの奥底から笑みを引き出した。 『だとう 塔矢アキラ!』 『塔矢にあわせてくれてありがとう』 そして隅に窮屈そうな字で 『オレは元気だ』 「アハハ‥‥」 声が溢れた。 口元を拳で押さえる。 けれど、溢れる笑みは抑えられなかった。 「『塔矢』は漢字で書けるのに、『打倒』は、ひらがななんだ‥‥」 おかしいのと楽しいのと、嬉しいのが混ざり合って、アキラは抑えた声で笑う。 ヒカルの行動は本当に、突拍子もなくて。 だからいつも、取り繕う間もなく怒らされたり、嬉しくさせられたりする。 アキラは絵馬の向きを元に戻すと、自分のものを外して、再び授与所へ向かった。 「塔矢!」 鳥居の方から、ヒカルが駆けてきた。 「進藤‥‥キミ、どこへ行っていたんだい?」 ヒカルは走ってきたためか、頬を軽く上気させ、白く息を弾ませていた。 「緒方先生来てたから、挨拶してきた。お年玉くれるかなと思ったんだけど、やっぱダメだった」 「それは‥‥そうだろう」 アキラはあ然としてヒカルを見つめる。 ヒカルがアキラの手元に気がついてのぞき込んだ。 「あれ、塔矢、まだ書いてなかったのか」 おっせーなぁ、とヒカルが悪戯っぽく笑う。 アキラは少しムッとして言い返した。 「いいだろう、別に。書いたんだけどね、書き足そうと思ったんだよ」 授与所でペンを借りて、ヒカルに背を向ける。 ヒカルは気にするふうもなく、後をついてきた。 「書き足すの?どんなこと?」 アキラは立ち止まると、くるりと振り返った。 「『進藤に会わせてくれてありがとう』」 「とっ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥!!」 ────この時のヒカルの顔といったら。 アキラは弾けたように笑い出した。 ヒカルが顔を真っ赤にして怒鳴った。 「塔矢!おまえ、オレの読んだだろう!」 「だって、一枚だけ裏向きだったから。直そうと思ったら、目に入っちゃったんだよ」 「直すなよ、いちいち!」 「分かった。これから気をつけるよ。それでいいかな」 「‥‥っ、よっ、読んだの忘れろ!忘れてしまえ!」 ヒカルが飛びついて、アキラの髪を思いきりぐしゃぐしゃとかきまぜた。 「ちょっ、こらっ、進藤!」 ヒカルを振り払って、アキラは髪を振り乱したまま怒鳴った。 「子どもか、キミは!」 ヒカルの行動はやっぱり、突拍子もなくて。 ────だからいつも、取り繕う間もなく怒らされたり、嬉しくさせられたり。 そう、いつも、本当の〈アキラ〉を引っぱり出してしまうのだ────進藤ヒカルは。 少し離れたところで、市河と芦原が二人の様子を見ていた。 「あ〜あ、またやってるわ。あの二人」 「きっと今年も一年、あんな調子なんだろうな」 呆れた口調とは裏腹に、二人の表情はやわらかい。 「あ、塔矢先生!」 市河が鳥居の方に塔矢夫妻を見つけて手を挙げた。 「先生!ほら、以前ご覧になりたいっておっしゃってた〈子どもっぽいアキラ君〉!そこでやってますよ。進藤君と」 「そうか」 言葉少なに、夫妻がやってくる。 表情の乏しい行洋のかわりに、明子が興味深そうに瞳を輝かせていた。 「だいたいおまえ、人の書いたヤツ、パクんじゃねぇよ!」 「パク‥‥ボクが書きたいと思うから書くだけじゃないか!真似してるわけじゃない!」 「いーや、パクリだ。パクリ」 「違う!」 「違わない!」 「あら、ホント」 明子が楽しげにコロコロと笑った。 「アキラさんがお友達とあんなふうにしているところ、初めて見たわ。ねえ、あなた、あの二人、連れて帰ってもよろしいかしら?ご近所の方もみんな見ているようですし」 「そうだな」 「あ、じゃあオレ呼んできますよ」 「そうですね、早くしないとまた例のパターンになるかもしれませんものね」 市河の言葉に、行洋と明子が不思議そうに振り返る。 ヒカルの大声が届いたのはその時だった。 「帰る!!」 「ほら、出た」 市河と芦原が苦笑する。 行洋は驚いたように目を丸くし、明子はさらに声をたてて笑った。 「で、どうしますか?」 問いかけた芦原に、明子は笑いながら言った。 「悪いんだけど芦原さん、進藤君をお誘いしてきてくださる?」 「あ、はい、分かりました」 芦原が、足早に離れていくヒカルの方へと走っていった。 「アキラくんの方は、どうしますか?呼んできましょうか」 市河が尋ねる、 「そうね、放っておいても帰ってくると思うのだけれど」 明子は楽しげな笑みを夫に向けた。 「あなた。お正月ですから、子ども達と遊んでやってくださいな。たまにはよろしいでしょう?」 「ああ‥‥そうだな」 行洋の口元がわずかにゆるむ。 それで、彼もこの状況をずいぶんとおもしろがっているのだろう、と市河も知ることができたのだった。 「アキラくん!」 市河が通る声で呼びかける。 振り返ったアキラはひどく驚いたように目を丸くしたかと思うと、どこかばつの悪そうな様子で、ゆっくりと近づいてきた。 鳥居の方から、ヒカルが芦原と共に戻ってきた。 |
|
| 2002.12.31 |